この1冊(書評集)
◆『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』マックス・ウェーバー 岩波文庫 1989年(新訳版)
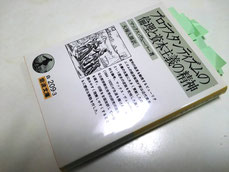
通称『プロりん』。長く読み継がれてきている比較宗教研究的社会学の古典である。
24歳で初めて手にして以来、こちらの教養の無さに加えて、脚注表記の多さや錯綜する論理展開ゆえに挫折すること数回。
だが、その面白さがわかるようになってからは、ベルリンの壁崩壊、リーマンショック、米トランプ政権による混乱など資本主義のあり方が問われるたびに読み返してしまうため、いまでは書き込みだらけになってしまった書である。
さて、その骨子。何ゆえに西欧キリスト教からくる自己抑制的・禁欲的な価値観(プロテスタンティズム)が多数を占めていたイギリス、フランス、オランダなどの地域にむしろ集中するかたちで資本主義が高度に発達したのか。
単純な経済動機では説明できない相矛盾するこの現象について、「天職(Beruf)=それぞれの仕事は天から与えられたミッションである」という思想をテコに、「内的禁欲」を「行動的禁欲」というエートスへ昇華させることを通じて、実は(利潤を敵視する)プロテスタンティズムが資本主義の成立に多大な貢献をしたのではないか、といった実に興味深い論考を試みているのである。
私にとっては「自分のミッションや天職をどう考えていくのか」など根源的なことについて、現在に至るも示唆を与え続けてくれている「常に側に置いておきたい書」である。
2017年4月17日(月)記
◆『連戦連敗』安藤忠雄 東京大学出版会、2001年(2011年第11刷)

2017年4月12日(水)記
◆『孤独の研究』木原武一、PHP出版、1995年.
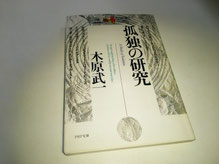
この世に生まれて以来、多くの人が、学校でも会社でも親類縁者間においても、いつも教え込まれてきたのは、人といかに上手くつきあうかといった協調性を身につけること、お客さんや上司など相手の立場に立ってものを考えたりすること、よき家庭人であること、といったことばかりである。
チームワークしかり、顧客第一主義しかり、忖度(そんたく)しかり....
だが、これらがあまりに優先されてしまうと、周囲の評価を得やすいことと相まって、いつしか他者に合わせることが空気のように常態となってしまい、自分がどう生きたいのか、生きるべきなのかが分からなくなってしまう、あるいはそういった問題意識さえ忘れ去っていってしまう、と私は思う。
人が生きていくうえで、まずやらねばならないのは、自分がどういう生き方をしたいのかについて、誰にも頼ることなく、自身の力で心の奥深くからそれを引き出し、つくりあげていくこと、さらには、その過程を通じて悩み苦しむことである。
他人とのつきあい方は、社会における集団活動が否応なく教えてくれる。しかし、自分自身といかに向き合うかについては、ほとんどの人が教わることがないまま歳を重ねていく。
本著『孤独の研究』では、(自らの身を置き換えての)主体的洞察力を持った文筆家・木原武一が、孤独を生き抜いた9人の生きざまに対するすぐれた考察を通して、
◆ひとりの人間が、自分とどう向き合い何を得ていくべきなのか
について、興味深い示唆を与えてくれる。多くの人が求めるものと「逆行」する稀少な書である。
2017年4月2日 記
◆『occam2 Reference Manual(オッカム2 リファレンス・マニュアル)、インモス社刊 1990年』
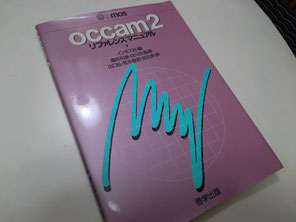
書庫をひっくり返して探しものをしていたら、何ともなつかしい書籍が出てきました。いまはなきインモス社が刊行した『occam2 Reference Manual(オッカム2 リファレンス・マニュアル)1990年刊』。20歳代前半、開発をやっていたころに購入したものです。
occamは、1980年代、並列処理時代の到来の象徴として登場した並列処理特化型マイクロプロセッサ「トランスピュータ」向けに構成された並列処理プログラミング言語です。当時はその概念のおもしろさと次世代コンピューティングに対するワクワク感とが相まってずいぶんと勉強したものですが、その後のチップ集積度数の(予想外の)飛躍的な進展によりその存在は忘れられていきました。
しかしその理論の要諦は、CSP(Communicating Sequential Processes=並行性に関する計算理論)やGoogle社のGo言語、スパコンなどに引き継がれ、しっかり生き残っています。何よりも、トランスピュータが登場した背景にある回路集積度という本質的な問題はいまだ解決されておらず、さらにはクラウド&エッジコンピューティングによる大型IoTシステム時代の到来で、ふたたび日の目をみる機会がおとずれる可能性は、個人的にはあるのではないかと思っています。
しかし、開発者として燃えていたころを思い出しますね。時間ができたら勉強し直してみようかな??
2017年2月10日:記
◆『限界費用ゼロ社会 〜モノのインターネット(IoT)と共有型経済の台頭』ジェレミー・リフキン著 2015年10月刊

世界中で、ゾクッとさせるほど大きな地殻変動が起こっていることを感じさせてくれる書です。
その内容はというと...IoT(Internet of Things)、CPS(Cyber Physical System)という世界的な潮流よってあらゆる主体がつながり、さらには情報、エネルギー、輸送が極限まで効率性・生産性を高め、世界中の人々の共有インフラとなって事業の限界コスト(事業参入・運営コスト)がかぎりなくゼロに近づく。
これにより、社会やコミュニティが「共有(シェア)すべき価値のあるもの」すなわち「共有価値=社会への貢献価値」をあまねく水平的に、(社会性のある)適切な均衡点を保った利益のみを得ながら分配できるしくみを創出できる人が主導権を握っていく、といったパラダイムの大転換がとなえられています。
たとえば、配車サービスで世界展開するインターネット企業「Uber」(ウーバー)が、なぜ世界中で受け入れられているのか、なぜパナソニックや日立をうわまわる時価総額5兆円の値をつけているか、の意味がわかります。
別な言い方をすると、「希少性」「非対称性」「独占性」に利益を乗せて交換する、といった旧来型の商売をしてきた資本主義型の経済システムが、主役の座からおりねばならない、ということを意味しているんですね。
数々の問題を露呈してきている資本主義が衰退していく。...これも「神の見えざる手」が働いているということなんでしょうか。
久々に事業欲を刺激される、とてもエキサイティングな読み物でした。
2015年11月26日:記
◆『価値共創の未来へ 〜顧客と企業のCo-Creation』C.K.プラハラード著、ランダムハウス講談社、2004年
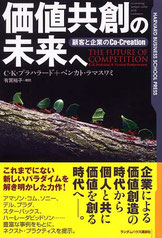
数年ぶりにこの本を読み返しました。
名著『コア・コンピタンス経営』の著者として、コア・コンピタンスということばを一般化させたC.K.プラハラード氏による力作です。
その要旨ですが、マス市場ではなく「個」を中心にすえ、顧客が製品を活用することにより得られるさまざまな快適経験を顧客と共創していくこと、そのために「モノ売り」ではなく、ITによるサービス・プラットフォームにビジネスモデルをシフトさせることの重要性を緻密な論理で展開しており、まるで現在のIoT(Internet of Things)やCPS(Cyber Physical System)の到来を予言するかのような内容となっています。
たとえばアメリカの大手農機具メーカー「ジョン・ディア」社の例。
農場主が同社のコンバインやトラクターを利用して農作業を終えるまでの全工程において、ITをもちいて遠隔監視・コントロール、作業にともなうリスク管理、マシンチューニング等のサービスをリアルタイムで提供し、顧客の農作業プロセスが円滑に完了するまで、まるでマラソンの伴走者のように顧客に寄り添うビジネスモデルが取りあげられているなど、現在においても十分に参考になる事例や考え方が盛り込まれています。
2015年11月19日:記
◆『並行プログラミングの原理―プロセス間通信と同期への概念的アプローチ』(1986年 M. ベン-・アリ)

埼玉県和光市の郊外に借りている書庫を整理していたら、二十数年前、システムエンジニアをやっていたころに買ったと思われるこの本が出てきました。
C.A.R.ホーアの理論をベースに、プロセス間の通信と同期に関する概念をセマフォなど各種テクニックで例示しながら、並行プログラミングの性質や証明方法、複数プロセス制御を効果的に行うためのプログラミング技術を解説した書籍です。
当時、近い将来の並列コンピューティング、マルチコア時代の到来をにらんで一生けん命勉強したことを思い出しました。残念ながら、並行プログラミングの世界は、この時代からほとんど進化していませんが。
.....それはともかく、中身をみたところ、確かにわたしの字で書き込みや線引きがなされているのですが、内容についてほとんど覚えていないどころか、自分のメモが何を言っているのか、まるでわかんないんですよね(涙)。
2015年11月15日:記
◆『ハーバードの医師づくり〜最高の医療はこうして生まれる』 (田中まゆみ・著/医学書院、2002年)

少し古い本で、そもそも米国には医療格差やさまざまな裏事情があることを前提としなければなりませんが、米国の医学教育の旗手とされるハーバード大学医学部における医師づくりが、基本マナー、インフォームドコンセント、患者第一主義、患者との相互理解によるリスクマネジメントなど、医療技術のみならず、プロフェッショナルとしての全人格的な育成をはっきりと視野に入れて行われている様子をうかがい知ることができます。
また、昨今、大学や欧米の研究機関では、さまざまな人種・職種からなる多様な価値観を混ぜて新たなケミストリーを創出しようとする動きが顕著になってきていますが、ハーバード大学医学部では、いち早く「多様な人材を混ぜる教育(7ページ〜)」に意識して取り組んでおり、この点でも先行者としての興味深い示唆が得られます。
2016年6月29日:記




