最終更新日:2017年4月8日(土)
過去のトピックス−1
◆2018年1月6日:あけましておめでとうございます。本年は、沖縄の大規模国際物流拠点から仕事はじめのご挨拶です。

2017年1月、あけましておめでとうございます。
本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。
さて、2017年の弊社の仕事はじめは、沖縄県が東アジアの物流ハブとして力を入れる那覇地区の国際物流拠点からとなりました。
沖縄から航空機で半径4時間圏内のアジアを中心とした地域には、約20億人のマーケットが存在(潜在)しているわけですが、この拠点を国際物流戦争の橋頭堡とすべく、各企業がこぞってこの拠点を中心とした国際物流ネットワークの形成に力を入れ始めています。
特に目立つのが、従来の物流専門家とは異なる領域のスペシャリストの姿が散見されること。国境を越えた国際物流戦争においては、IoT/ICTやAI(人工知能)、Data Analyticsなどソフトの分野における高い専門性が求められるわけですが、沖縄での展開は、それら最先端テクノロジーのビジネス戦略面における有効活用体制の構築支援を専門とする弊社にとっても大きなビジネスチャンスとなっています。
月並みな表現で恐縮ですが....今年も全力投球でがんばります。
引き続きご支援のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。
◆時代はオキナワ!.....9月13日(火)〜16日(金)に東京ビッグサイトにて開催された「国際物流総合展」に行ってきました!

時代はオキナワ!!!
.....9月13日(火)〜16日(金)に東京ビッグサイトにて開催された「国際物流総合展」では、ANA、ヤマト運輸、沖縄県が、沖縄を東アジアの物流ハブ・戦略拠点ととらえて出展した共同ブース「OKINAWA Bridging Asia」がひときわ目をひきました。
実は弊社も沖縄の未来をにらみ、事業への戦略的な投資や経済特区としての沖縄における実験的な取り組みへの参画・出資など、東アジアの中心点たる沖縄に橋頭堡を築くべく、さまざまな活動を展開しています。
ちなみに、沖縄から航空便で4時間圏内には、約20億人の巨大マーケットが広がっています。
さらには沖縄県は、出生率=全国1位、若年人口割合=同1位、人口増加率=東京に次ぐ2位という高い水準にあり、平成27年度の那覇空港の国際貨物取扱高は、同20年度比の約100倍となる17万7千トンにまで達していて、さらに増加する傾向にあります。
インターネットの世界展開を追うかたちで、世界の主要地域における「国際物流ネットワーク」構築・再編成の動きが加速してきたいま、まさに沖縄は、かつて東アジアのハブたる貿易立国として栄えた「琉球・南海王国」の胎動を感じさせてくれるんですね。
◆2016年6月17日(金)、気鋭の技術価値創造企業「AZAPAグループ」のトップ・マネジメントとともに、未来をめざして歩み続けています!

田中が顧問をつとめ、技術マネジメント人材の育成を指導している気鋭の技術価値創造企業「AZAPA(アザパ)」グループのトップ・マネジメントの面々と。
先週、同社で行われた恒例の「トップ・マネジメント研修会」の終了後に記念撮影です。この日は、最高レベルの価値・成果を生み出す組織体制や人材モデル、スキルセットについて突っ込んだ議論を行いました。
写真・前列右がグループ全社を率いる近藤康弘CEO、中央がわたし、左がトヨタ自動車で30年近くにわたり制御理論・ソフトウェア技術を追求してこられた役員の伊豫田(いよだ)さん、後列は、同社の若き幹部の面々。
AZAPAグループは、自動車パワートレインの中核であるエンジン制御や燃焼メカニズムの領域において、最先端のモデルベース開発やシミュレーション技術などを駆使して培った高度な理論開発力&具現化力、価値創造的な開発力をコア・コンピタンスとして、環境システムや再生可能エネルギー、社会インフラとしてのモビリティ・マネジメントなど、自動車にとどまらない領域における価値の創造、世界のBOP市場への貢献をめざして、進出した各国・各地域で躍進を続けています。
◆2015年5月27日(金)、某ICT系上場企業さんの創立記念日にて『IoT時代の価値デザインと人材育成』というテーマで基調講演を行いました。

少し前の話ですが、2015年5月27日(金)、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の「はやぶさ1〜2号」プロジェクトへのメインプレーヤーとしての参画など、高度な技術力で知られる某大手エンジニアリング企業A社さんの創立記念日式典において、『IoT時代の価値デザインと人材育成』というテーマで基調講演を行わせていただきました。
都内の本社ビルで行われた当日の模様は、地方の全支社へも生中継され、社長・役員・顧問の方々などトップマネジメント以下、全社員数百人のみなさんに向けて、私が考えるIoTの本質やめざすべき方向性、IoTを持続発展的に進化させるための有効なサービスデザイン手法、IoTをマネジメントできる人材の育成などについて、あますところなく語らせていただきました。

活発な質疑応答もいただき、その後の食事会でも引き続き議論が交わされるなど、幹部の方々から「かなりの刺激になった」とのお言葉を頂戴し、私にとってもまさに刺激的な一日となったのでした。
A社のみなさん、ありがとうございました。

◆2016年5月21日(土)、ドラッカー学会総会にて、立命館アジア・パシフィック大学の創設者にして初代学長で大親友の坂本和一先生と。

5月21日(土)、設立10週年をむかえて、わたしが客員研究員をつとめる明治大学にて行われた「第11回ドラッカー学会総会」の懇親会にて。
写真右は、ご存じ、大学革命の旗手として知られる「立命館アジア・パシフィック大学」の創設者にして初代学長、わたしがもっとも敬愛する教育界のイノベーター、(僭越ながら)大・大・だ〜い親友の坂本和一先生。
この日も、以前から意見交換を続けさせていただいている、立命館APUと沖縄先端科学技術大学OISTの間ではじまった文理融合のための交流や、おなじく文理連携の潮流を端的に示すIoT、わたしが所属する産業技術総合研究所でとりくんでいる技術マネジメントの話題などで意気投合!!
さらには、立命館APUがあり、わたしが支援を行う予定の大分県の某公的シンクタンクのくわしい内部事情を偶然、先生も熟知していらっしゃるなど、坂本先生とお会いすると、いつも不思議なくらい話が盛り上ってしまい、メチャメチャ楽しい時間となってしまいます。
ちなみにこの日、日経BP社より、坂本先生をはじめとする、立命館APU創設のために奮闘した方々の足跡を追った『混ぜる教育 〜80カ国の学生が学ぶ立命館アジア太平洋大学APUの秘密』が刊行されました。
※本コラムは、坂本和一先生ご本人に内容をご確認いただいています。
◆2016年4月19日、新進気鋭の自動車制御・環境技術ベンチャー「AZAPA社」のトップマネジメント勉強会の風景です。

わたし・田中(写真中央)が技術顧問をつとめ、全社マネジメントの指導を行っている新進気鋭の自動車制御技術系ベンチャー「AZAPA社」(アザパ/本社:愛知県名古屋市)における、近藤社長(右から3人目)以下、トップマネジメント・チームの勉強会の風景です。
今回のテーマは、ズバリ「技術人材の育成とマネジメント」。
同社は、博士号保有者を中心に、トヨタ自動車などで次世代自動車・環境技術を追求してきたメンバーで構成され、特にモデルベースド・ソリューション、エネルギーマネジメント、エンジン制御理論開発などで大手を凌駕する強みを持つ企業です。
高度な技術力に甘んじることなく、技術・エンジニアリング力を事業の戦略展開に生かし、優秀な人材をマネジメントする力を組織の中核能力にまで高めるべく、日々学習し、進化を続ける素晴らしい集団なんですね。
●AZAPA社紹介ページ(動画):
http://www.azapa.co.jp/recruit/index.html
◆2016年2月23日(火)、テレビ朝日『TOKYO応援宣言』の企画で、日本発の最大のイノベーションの1つ「ピクトグラム」についての対談が行われ、田中も企画実現のお手伝いをさせていただきました。

2016年2月23日、テレビ朝日の番組『TOKYO応援宣言』の企画で、スポーツコメンテーター・松岡修造さんと、田中と家族ぐるみのおつき合いがある版画家・原田維夫さんの対談が行われ、この企画の実現をお手伝いさせていただいた田中も応援に駆けつけました。
当日は、原田先生がデザイナーとして参加した「1964東京オリンピック」で開発され、世界に広まっていき、日本発の一大イノベーションとなった「ピクトグラム」について、約1時間にわたり、松岡修造さんと原田先生が、熱く語り合いました。

この模様は3月上旬に放送される予定で、日にちが決まり次第、このサイトでも告知します。
みなさん、どうぞお楽しみに!!
※各写真は、番組が収録された原田先生の工房(港区・白金高輪)にあるスタジオでのものです。
●詳しい対談の模様:
◆2016年2月12日、わが心の師、日本一のギタリスト、松原正樹さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

セッションミュージシャンをやっていた若かりしころに大変お世話になった日本一のギタリスト、松原正樹さんが2月8日に逝去されました(享年61歳)。
松原さんは、ユーミンや松田聖子、中森明菜、矢沢永吉、松山千春、さだまさしなどそうそうたるアーチストをはじめ、1万曲を超えるレコーディングに参加された、掛け値なし日本一、いや(私にとっては)世界一のギタリスト・ミュージシャンでした。

上の写真は、80年代、私がサポートミュージシャンとして参加したある女性シンガーのコンサートで、同じくメインギタリストとして参加されていた松原さんに、リハの合間にギターの手ほどきを受けているときのもの。
下の写真は、同時代、渋谷にあった「LIVE-INN」で松原さんのライブが行われたときに、楽屋でごあいさつさせていただいたときのものです。
...とても心優しい方でした。クラシック出身でポピュラーミュージックになじめず、パッとしないミュージシャンだった私を可愛がってくださり、あの、独特の美しく伸びやかなギターフレーズや絶妙のテンションコード・カッティングを、目の前で、私のためだけに弾いてくださいながら、音使いのポイントや“楽器を歌わせる”コツなどを親身になって伝授してくださったことが忘れられません。
弦楽器奏者として、お互いに手が小さかったことをよく話題にしていたのですが、訃報をお聞きして、改めて松原さんの小さくてふっくらした手の感触を思い出してしまい、いまも涙が止まりません。
相手の立場に立った真摯な姿勢、オープンなマインド、プロのセッション・ミュージシャンとして黒子に徹することの意味と意義、自分の感性を信じること、創造性と技術が相互補完の関係にあることなど、いまの私があるのは、大切なこれらのことを松原さんから学ぶことができたおかげです。
松原正樹さんのご冥福を心よりお祈りいたします。
◆2016年1月27日、【組織改編・社名変更のお知らせ】株式会社ジェイ・ティー・マネジメントとして再スタートを切りました!

昨日27日より弊事務所は「株式会社ジェイ・ティー・マネジメント」(Japan Technology Management Inc.)として再スタートを切りました。
(旧事業者名:ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所)
引き続き、IoT/CPS(Cyber Physical System)を戦略コンセプトの中核とし、イノベーションを通じた企業再生、ハイテク系企業のM&A、技術戦略コンサルティングの3つを業務の中心にすえていきます。
また、これらを強力に推進する体制として、M&Aスキームや知的財産戦略に精通する法律家、IoT領域における博士号・研究経験を有する技術コンサルタントなどのスタッフもさらに増強し、米国系投資ファンドや内外の有力な研究機関とも密に連携しながら事業を推進していきます。
今後も変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたします。
(日比谷オフィスの住所や連絡方法など、組織形態・社名の変更以外はこれまでとまったく変わりありません)
株式会社ジェイ・ティー・マネジメント
代表取締役社長 田中 純
◆2015年12月10日(木)、明治大学の客員研究員として、学生たちに講義を行いました!

明治大学の客員研究員として、駿河台の本校舎で講義を行いました。
情報組織論の第一人者・阪井和男教授にお招きいただき、学生の正規の授業の一環として、私の実戦経験をもとに、技術戦略とビジネスモデルの関係性や、グローバル市場でどう戦っていくかについてしゃべらせていただきました。
◆2015年11月11日(水)、産業技術総合研究所が主催する「第6回ロボットイノベーション・コンソーシアム」にて講演を行いました!

11月11日日水曜日、世界最先端を走る、わが産業技術総合研究所・ロボットイノベーション研究センターが主催する「第6回ロボットイノベーション・コンソーシアム」で講演を行いました。
題して『グローバル時代におけるビジネス・エコシステム戦略と人材育成』。
技術・知財では依然として優位にある日本企業がなぜ世界のビジネスで勝てないのか。なぜコスト競争に巻き込まれ、市場撤退を繰り返してしまうのか。

そのメカニズムとグローバル市場で戦うための技術・知財マネジメントのあり方について、詳細な市場データや欧米IT企業のビジネスモデルの分析事例などをもちいながら、1時間30分にわたりしゃべらせていただきました。
そうそうたる企業のロボティクス分野における技術者・研究者、事業担当者などが来ておられましたが、質疑応答も活発に行われ、講演後も個別に相談を受けるなど、皆さまにはある程度のご満足をいただけたように思います。
◆2015年10月30日(金)、「第14回 日本イノベーター大賞 特別賞」に友人であるZMP社長の谷口 恒さんが選ばれました!

日経BP社が主催する2015年度「第14回 日本イノベーター大賞 特別賞」に、友人であるZMP社長の谷口恒さん(写真右)が選ばれました!
おめでとう、谷口さん!!
【選考理由】日経BP社HPより:
-----高速・高精度に位置を推定する自動運転システムを開発。標識や位置情報に頼らずカメラやレーダーで位置を特定する『SLAM技術』を採用。
今年、DeNAと合弁で無人タクシーの事業化を目指す『ロボットタクシー』を設立するなど、ベンチャーながら大手自動車メーカーに負けない先進性がある-----
◆2015年10月23日(金)、SCSK社の皆さんと「ニュートンのりんごの木」の前で。産総研テクノブリッジフェア2015年より。

10月23日(金)、わが産業技術総合研究所が、最先端技術をもつ日本の有力企業をお招きして開催する「テクノブリッジフェア2015」が無事終了しました。
写真は、いま、いちばん注目されている企業といっても過言ではない、住友商事グループ系の大手IT企業「SCSK社」の幹部のみなさんと、産総研つくば本部の敷地内にある「ニュートンのりんごの木」(ニュートンの木の孫木)の前での記念撮影です。
(写真左から田中、住商アビーム自動車総合研究所の大森社長、SCSK社の経営幹部/研究所幹部四人さま、最右が並列計算アルゴリズム理論の第一人者・弊所の磯部研究員)
SCSK社は、日本経済新聞社が実施した2014年の「人を活かす会社」調査において総合ランキング1位、東洋経済新報社が実施した2015年の「CSR企業ランキング」調査において人材活用分野1位となるなど、いまノリにノッている企業さんです。
この日は、技術展示ツアーや弊所幹部・トップ研究者との交流、シメの懇親会にいたるまで、まる一日、濃密な時間を共有させていただきました。
◆2015年10月13日(火)、自動運転ロボカー・ロボット分野の風雲児、技術ベンチャーの雄「ZMP」社の谷口亘社長と大いに語り合いました!

写真右から、ロボット・自動運転の分野における台風の目、ビジネス系の新聞やニュースではその報道を見ない日はないという技術ベンチャーの雄「ZMP」社の谷口亘社長、田中、
探査衛星はやぶさ1,2号の内部ソフトウェアの開発設計を担当し、同プロジェクトを技術力で支えたセック社の秋山逸志社長。
(2015年10月13日撮影)
谷口さんはDeNAとの合弁会社「ロボットタクシー」社の会長もつとめており、2020年の東京オリンピックをめざして完全自動運転によるロボットタクシーの実用化をめざしていることはよく知られていますね。
この日は事業家どうし、お互いの会社の内部事情からはじまり、自動車やロボットの未来、はては日本の産業のあるべき姿についてまでも大いに語り合い、飲み食い、今後のさらなる協力を誓い合ったのでした。
◆2015年9月11日(金)、東京大学名誉教授で「報道ステーション」コメンテーターの月尾嘉男先生の事務所を訪問しました!

テレビ朝日「報道ステーション」やTBS「ニュースバード」などメディアにおけるコメンテーターとしても活躍されている東京大学名誉教授の月尾嘉男(つきおよしお)先生と。
月尾先生に招かれて、数寄屋橋にある先生の事務所に遊びに行ってきました。ある著名な芸術家さんの紹介で知りあったのですが、お互いにウマが合うのか、とてもよい関係を続けさせていただいています。
気さくながら私のような者にも礼儀をわきまえて接してくださるお方で、会うたびに、先生のお人がらに惹かれていってしまいます。
きょうは、わが産業技術総合研究所の取り組みについての議論に始まり、「報道ステーション」の古舘伊知郎キャスターとの交流や、今回モメにモメている国立競技場・五輪エンブレムの入札にかかわる(口がさけても言えないような)ウラ話まで、話題が尽きることなく、あっという間に時間が過ぎてしまったのでした。
◆2015年9月7日、知財戦略の第一人者、東京大学の小川紘一先生にお会いしてきました!

知財戦略の第一人者で、名著『オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件』の著者として知られる、東京大学の小川紘一先生と。
(2015年9月7日、ドラッカー学会における田中の友人、和田憲一郎さんが仕掛け人の自動車関係者の勉強会の懇親パーティにて)
わたしが所属する産業技術総合研究所/情報・人間工学領域 研究戦略部が主導するCPS(サイバー・フィジカル・システム)についての取り組みを詳しくお話させていただいたところ、話が盛りあがり、意気投合!
「きょうの最大の収穫は、あたな(田中)と出会えたことだ」という何ともありがたいお言葉をいただいたばかりか、近いうちに小川先生の研究室を訪問させていただき、具体的なコラボレーションの可能性を探ることになりました。
◆2015年5月29日(金)、著書『技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか』で知られる妹尾堅一郎(せのおけんいちろう)先生にお会いしてきました!

ロングセラー『技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか』で知られる、知財戦略やビジネスモデルに関する研究がご専門の妹尾堅一郎先生(NPO法人 産学連携推進機構理事長/一橋大学院客員教授)にお会いしてきました。
(ドラッカー学会の友人、和田憲一郎さんが仕掛け人の勉強会「自動車百年塾」の懇親パーティにて)
妹尾先生とは、日本の技術戦略に対する問題意識はもちろん、お互いに共通の知人がいたり、先生ご自身が(わたしが籍をおく)産業技術総合研究所のためにご尽力いただいていることもわかったりして、まさに意気投合!
この日、妹尾先生の講話があった文京シビックセンターから、懇親パーティ会場の東京ドームまでの道のりを、ずっと語り合いながら移動し、懇親会でもとなりの席に座らせていただき、たっぷりと意見交換させていただきました。
ちなみに妹尾先生は、現在わたしが参謀役をつとめる産総研/情報・人間工学領域のトップ・関口智嗣(せきぐちさとし)との共著『グリッド時代 技術が起こすサービス革新』(アスキー)も出されています。つまり、田中がいままさに一緒に仕事をしている関口とも同志という間がら。
何ともうれしいご縁もあることがわかって、とてもハッピーな一夜となったのでした。
◆2015年6月現在、ドラッカーのマネジメント&イノベーション理論を基盤とした幹部社員教育プログラムが大好評です!

先日、大手IT系上場企業・S社で行われた幹部社員教育の風景(右から2人めがわたし)。
わたしたち「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」は、ドラッカー理論をベースとしたマネジメント&イノベーション実践理論の普及をめざすべく、教育プログラムを複数コース開発し、上場企業をはじめとする10社以上において展開しています。
今回のサポート講師は、わが「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」の主力メンバーで、IHI社で長年開発を手がけてきた高部茂さん(写真いちばん右)です。
写真中央は、東大発ベンチャーだったS社を上場企業にまで育て上げたA社長。左のお二人は、同社の次世代をになう幹部社員です。
◆2015年5月13日(水)、日本ロボット学会の会長、早稲田大学教授の高西淳夫先生にお会いしてきました!

2015年5月13日(水)、日本ロボット学会の会長で、ヒューマノイド/医療・福祉ロボット研究の第一人者、早稲田大学教授の高西淳夫(たかにしあつお)先生にお会いしてきました。
写真右より、わたし、今年4月より日本ロボット学会の会長に就任された高西淳夫先生、IHIのもと開発責任者で現在は自動車に標準搭載されているスーパーチャージャーの発明者としても知られる高部茂さん。
訪問先は、東京女子医科大学・早稲田大学連携 先端生命医科学研究教育施設「TWins」(新宿区)です。
ここでは、おもに最先端の生命医科学に関する研究を推進していますが、名だたる企業の社名が掲げられた共同研究室がいくつもあり、高西先生みずからのご案内により、それらをふくむ主な研究室をいくつも訪問させていただき、数々のすばらしい研究成果を目の前でじっくり拝見する、といった珠玉の時間を過ごさせていただきました。
さらには、これからの研究活動のあり方や、事業化をにらんだ研究者と各種の専門家の連携体制等々について、長時間にわたり意見交換をさせていただきました。
高西先生ご自身については、医療技術とロボティクスを融合させた実用性・市場性ともに高いポテンシャルが感じられる研究をされており、そのいくつかは、すでに医療機器メーカーから製品化されて世の中に送り出されています。ロボットによる医療技術の進化促進、という新しい市場の先駆者としても大活躍されているんですね。
産総研において研究マネジメントに携わる者として、数々のヒントや知的な刺激を受けることができ、とても充実した一日となりました。
◆2015年4月25日(土)、dSPACE社日本法人の前社長、横浜スマートコミュニティ代表の有馬仁志さんと、新しいビジネスについて語り合い、有意義なひと時を過ごしました!
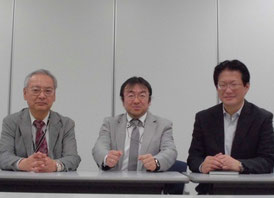
右から、前dSPACE社・日本法人社長、横浜スマートコミュニティ代表で、十数年にわたるおつき合いがある大親友の有馬仁志さん、田中(わたし)、IHIグループの開発部門を長年リードしてきているドラッカー学会のキーマン、高部茂さん。
(4月25日(土) IHI回転機械・豊洲本社にて撮影)
有馬さんは、日本において、かつて携帯電話などで大きなシェアを占めた組込みLinuxOS市場や、HILSとよばれる、数理モデルによる制御系シミュレーション・システムの市場をゼロから創造した産業用IT業界のスーパースターです。
特に、デミオなどスカイアクティブ技術を搭載したマツダ社をはじめとする自動車各社や、先日お目見えしたホンダジェットなど、イノベーティブな開発案件に貢献し、メーカーの開発のあり方そのものに大きな影響を与えた人として、経営学の教科書にも登場するような人なんですね。
この日は、IHI回転機械さんの本社で打ち合わせを行い、そのあと三人で飲み会をやったのですが、新しいビジネスのアイデアがどんどん湧いてきて、深夜まで話がつきることがありませんでした。
◆2015年4月8日、「明治大学サービス創新研究所」の客員研究員に就任しました!

4月8日より「明治大学サービス創新研究所」の客員研究員に就任しました。
ここにはドラッカー学会の仲間たちが何人かいて、ユニークな研究活動をやっているので、なかなか楽しそうです。
ちなみにここでは、私が籍をおく産業技術総合研究所における研究者の能力開発プログラムの構築や、技術イノベーション・マネジメント理論などを研究テーマにしていく予定です。
◆2015年2月7日、イノベーターお二人の感動的な出会いの瞬間に立ち会うことができました!

二十年の時を超えて、イノベーターの両雄が相まみえる!
写真左からもとマツダ社のエンジニアリング本部長で、同社のスカイアクティブ・テクノロジーが生まれる土壌となった全社プロジェクト「MDI=マツダ・デジタル・イノベーション」を、責任者として90年代半ばから十年にわたり率いてこられた滝口哲郎さん(現ネットシェア代表、産業技術総合研究所/協力研究員)。
写真中央が、90年代、マツダ社とともに、(いまは多くの自動車に標準搭載されっている)世界初となる画期的なエンジン過給システム「スクリューローター式スーパーチャージャー」を開発したIHI回転機械(当時はIHI=石川島播磨重工に在籍)の高部茂さん。いちばん右が私。
それぞれと親しくさせていただいている私の仲立ちにより、かつて同時期に、マツダ社を舞台としてイノベーションにチャレンジしてきたお二人が、二十年の時を超えて初めて顔を合わせました。
もともと高部さんは、滝口さんのお名前だけはご存知だったとのことですが、先月NHKで放送された「プロフェッショナル〜仕事の流儀」でミスターエンジンとして取り上げられた現マツダ社常務の人見光夫さんなどを介してお二人はしっかりとつながっており、当時、同じ方向をめざして懸命に走っていたことがこの日改めて確認され、大いに盛り上がった一夜となったのでした。
(2015年2月7日(土)、品川プリンスホテルにて撮影)
◆2014年12月12日(金)、自動車技術ベンチャーの雄、AZAPA(アザパ)社の東京R&Dセンター・オープニングセレモニーで、田中が講演を行いました!

2014年12月12日、トップクラスの自動車制御技術をもつ、成長いちじるしいベンチャー企業「AZAPA」(アザパ)社の東京R&Dセンター(千葉県/柏の葉キャンパス)のオープニングセレモニーで、『意味的価値とイノベーション戦略』というタイトルで講演をやらせていただきました。

右は、AZAPA社を率いる近藤康弘社長。
すぐとなりにある東京大学の出身者が多数を占める同社のR&Dセンターは、つくばエクスプレスの「柏の葉キャンパス駅」前にある近代的なビルにあります。
同じつくばエクスプレスのつくば駅にある産総研に初めて来られた際、この柏の葉キャンパスのビルを見てひと目で気に入り、移転を即決されたとのことです。

当日は、名だたる自動車企業の方々はもちろん、リコーや日立オートモーティブ、アクセス社、住友商事など車載システム市場で新たな展開をはかっている電機メーカーやIT企業の参加も目立ち、いま、いちばんホットな自動車業界の縮図を見るような、大いに盛り上がったイベントとなったのでした。
◆2014年12月12日(金)、自動車技術ベンチャーAZAPA社(千葉県・柏の葉キャンパス)で、田中が講演を行います!

名古屋にある自動車制御技術ベンチャーの雄、AZAPA(アザパ)社の東京R&Dセンターのオープニングセレモニーで講演をやります。
産業技術総合研究所で最先端技術の展開を主導してきた者として、技術イノベーション戦略について語ります。自動運転技術やAI搭載など、いま一番ホットな自動車業界の最新動向についてご興味のあるむきは、ぜひご参加ください。
●お申込み「AZAPA×産総研 第2回技術交流会」:
http://www.adea-next.co.jp/event/detail.php?id=8
◆2014年11月21日、マツダ社でデジタル・イノベーションを手がけた滝口哲郎氏に、わが産総研の協力研究員に就任していただき、今後の研究戦略について意見交換を行いました。

10月1日付で、田中が所属する産業技術総合研究所/セキュアシステム研究部門の協力研究員に就任いただいた大親友の滝口哲郎さん(写真左)と。
(11/21(金) 東京ドームホテルにて)
滝口さんは、マツダ社のエンジニアリング本部長という要職をつとめてこられた方で、アテンザ(2014年度カー・オブ・ザ・イヤー受賞)、アクセラ、デミオなどの基盤となっているスカイアクティブ・テクノロジーを生み出した「MDI=マツダ・デジタル・イノベーション※」を、10年にわたり陣頭指揮してこられた自動車業界のイノベーターとして知られています。
その実績とお人がらから、マツダ社のみならず、トヨタ、日産、ホンダ、三菱など自動車各社の幹部からも慕われ、尊敬されている人でもあるんですね。
※マツダは、1996年から約10年の歳月をかけて、自動車開発プロセスをすべてデジタル化するという一大イノベーションを行いました。
◆2014年10月9日、友人の版画家・原田維夫さんのNHK総合・BSへの出演に際し、番組の取材・企画構成に協力させていただきました!

現在、NKKが局をあげて東京オリンピックを特集しています。
わたしも、1964東京オリンピックでピクトグラム・デザイナーとして活躍された友人で著名な版画家・原田維夫(はらだつなお)さんのNHK総合『ひるまえほっと』、NHK-BS1『東京オリンピックをデザインした男たち』への出演に際し、イノベーションの専門家として、おもに「社会イノベーションとしてのピクトグラム」という観点から解説を行うなど、取材や番組の企画構成に協力させていただきました。
写真は、NHK総合『ひるまえほっと』の生放送(10/9)を終了した直後のもの。
左から、番組司会の三好正人アナウンサー、ゲスト生出演した原田維夫さん、わたし、番組レポーターで、今回、密接な打ち合わせを繰り返したNHK首都圏放送センターの松尾衣里子さん。
今回の企画に際し、松尾さんなどNHK側とやりとりしたメールや電話は、数十回にのぼりました。
◆2014年9月4日、わが「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」の結成2周年記念、およびドラッカー学会所属の公認研究会化の祝賀会を開催しました!

9月4日(木)、わが「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」の結成2周年記念、およびP.F.ドラッカー教授が唯一公認する学術研究団体「ドラッカー学会」傘下の公認研究会になったことを祝して、都内ホテルのレストランの個室を借りきって、みなさんと祝杯をあげました。
幹事をつとめた宴会のプロ、Wさんのおかげで、おトク感あふれるグレードの高い宴席となり、みなさん、美味しい料理とお酒を心ゆくまで堪能しました。
3年目に突入し、10月から新メンバー2名が加わり、わが研究会から上場企業のドラッカー勉強会への講師派遣も決まるなど、活動にますますドライブをかけていきます。
これからも「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」をよろしくお願いいたします。
◆2014年7月15日、わが「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」が、ドラッカー学会傘下の公認研究会となりました!

【ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会、公認化のごあいさつ】
2014年7月15日付で、わが「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」(DMIK)が、「ドラッカー学会」傘下の公認研究会となりました。
今後、世界で唯一、ピーター・ドラッカー教授ご本人が公認され、上田惇生先生をはじめ、セブン&アイの伊藤雅俊名誉会長、トヨタ自動車の豊田章一郎名誉会長、グーグル社のエリック・シュミット会長、ファーストリテイリング社(ユニクロ)の柳井 正CEOなど名だたる皆さまを顧問や支援者にいただく学術研究団体「ドラッカー学会」の公認研究グループとして、同会のホームページ上での情報発信や全国大会での成果発表などが可能となりました。
内外を代表する企業(重工業、電機、創薬、情報通信、IT、国家研究機関など)の技術者・研究者出身の経営幹部層を中心に構成される「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」は、2012年8月に活動を開始して以来、来月でちょうど二周年となるゆえ、新たな年度への突入に向けて、今回の公認研究会化はよい節目となりました。
今後、新メンバーも加わる予定で、一同、ますます張りきっています。 改めて、「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」(DMIK)をよろしくお願いいたします。
【研究会の内容】
当研究会では、マネジメントとイノベーションというドラッカー理論の両輪をなす領域に対する実践面からの学びを深めるため、メンバーのほぼ全員を、国内外の企業のトップや事業・部門責任者などの要職に就いている実務家、および経営の実態をよく知る専門家(学術研究者・コンサルタントなど)で構成しています。
(さらには、難易度が高いといわれる「技術を基盤としたイノベーション」についての研究も行なうため、研究者や技術者の経験を有する理工学系の出身者を中心としています)
机上論にとどまらないマネジメント&イノベーションを実践してきているメンバーの知見を武器に、詳細なケース報告を題材にしながら、徹底的な分析とディスカッションを通じてドラッカー理論を掘り下げていく、というスタイルで研究活動を行なっています。
企業経営者、事業・部門責任者、経営管理職、研究開発プロジェクト責任者など、マネジメント&イノベーションを主導する立場にある方の参加を歓迎します。
(原則として毎月第一木曜日に開催。「報告・問題提起」と「理論研究会」を交互に行なっています)
※スケジュール等がご覧いただけます。
◆当究会へのお問い合せは、当サイト「お問い合わせ」ページよりお願いします。
◆2014年6月5日(木)、第11回「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会 〜さらなる飛躍をめざして」を開催しました。

◆第11回ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会を開催 ~さらなる飛躍をめざして
◯ ◯ ◯
2014年6月5日(木)、第11回「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」(DMIK)を開催した。
今回は、現在、京都の老舗サービス企業の某事業の責任者をつとめるNさんから、研究会の今後の展開戦略について数々のユニークな提言があり、それらについてメンバー一堂で詳細な検討を行った。
研究会という組織みずからドラッカーの教えを実践すべく、facebookによる社会とのコミュニケーションを通じた情報発信や成果物の構築、最近打診が増えつつある参加希望者への前向きな対応など、具体的な施策を新たに推進することが確認されたのであった。
※ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会にご興味をお持ちのむきは、お気軽にお問い合わせください。
※次回開催は7月10日(木)18:30~(芝浦/JR田町駅)となります。
→基本は毎月第1木曜日の開催ですが、次回のみ第2木曜日の開催となります。
(偶数月はメンバーからの報告&問題提起、奇数月はドラッカー理論の研究を行っています)。
◆2014年4月3日(木)、第10回「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」を開催しました。

◆第10回ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会を開催
~大企業サラリーマンの葛藤が示唆する日本の企業人の問題とは? 独立開業をめざすWさんからの報告。
◯ ◯ ◯
2014年4月3日(木)、第9回「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」を開催した。
今回は、現在、大手電子機器メーカーに(開発職を経て)営業責任者として勤務するWさんから、中小事業者の支援者(コンサルタント)として将来の独立をめざすための趣意や背景を網羅的に記述したプランの提示があり、その妥当性についての検証と議論が行われた。
メンバーからは、Wさんが提示したプランの妥当性や構成項目の優劣の評価にとどまらず、その背後にある自己分析の視点、はては他者との共感力などの基本的なコミュニケーション力や中小事業者に対する対峙姿勢にまで指摘がおよび、4時間近くにわたって、スリリングかつシビアな討議が続いた。
特に、みずから事業を立ち上げ日々奮闘している事業責任者のNさんや、200社を超える企業へのコンサルティング・企業再生の経験を有する田中からは、中小事業者の当事者としての目線や専門プロフェッショナルとして先行する者の立場から、遠慮のないきびしい指摘が行われたのである。
今回のWさんからの報告・問題提起は、多くの大企業サラリーマンが抱える問題の根の深さを示唆するものとなり、なぜ大企業が活力を失っていくのか、なぜ企業から独立した者の97%が5年以内に消えていくのか、なぜ日本の組織で企業家精神が育まれないか、なぜ大企業と中小企業・ベンチャー企業の間に深い溝があるのか、といった重要な問題を考えるうえでも有意義なものであったと思う。
最後に、皆からの指摘を真摯に受けとめ、さらに深くみずからに対峙することを約束して報告を締めくくったWさんの前向きな姿勢に、メンバー一同、あらためて(他の大企業サラリーマンとはひと味ちがった)その柔軟性と独立にかける思いに感銘をうけ、彼のさらなる飛躍を確信して研究会を終えたのであった。
※ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会にご興味をお持ちのむきは、お気軽にお問い合わせください。
※次回開催は5月8日(木)18:30~(芝浦/JR田町駅)、次々回開催は6月5日(木)18:30~(同)となります。
(偶数月はメンバーからの報告&問題提起、奇数月はドラッカー理論の研究を行っています)。
◆2014年2月6日(木)、第9回「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」を開催しました。

※写真いちばん右が、今回の報告者のMさん。上場企業である創薬治験企業の社長を退任されたあと、現在は新たな創薬ベンチャーにチャレンジ中である(写真いちばん左が田中)。
○ ○ ○
2014年2月6日(木)、第9回「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」を都内にある大手情報インフラメーカー本社で開催した。
今回は、小さな医療具取扱企業を創薬の治験を専門に行う企業として生まれ変わらせ、上場するまでに育て上げたMさんからの、きわめて生々しく、さまざまな思惑が交錯する医薬品業界に生きる企業ならではの経営のむずかしさを実感させられるような報告があった。
特に、紆余曲折を経て、わが子のように育てた企業からの別離を決断するまでのストーリーは胸に迫るものがあり、涙をこらえながら話に耳をかたむけるメンバーも何人かいたようである。
Mさんは、現在は新たに創業した創薬ベンチャーを率いて奮闘の日々を送っているが、そのまったく衰えを知らぬチャレンジ精神には、メンバー一同、頭が下がる思いである。
今回のMさんからの報告と問題提起は、当研究会における過去の研究事例の中でもトップクラスに位置付けられる充実した内容のものとなったのであった。
◆2013年1月25日、ブログ「いまだに道半ば ~大人になれない日本企業」をアップしました!

これは、20年以上も前から大前研一さんが提唱されている、企業が国際化していく進化の段階をモデル化したものである(一部加筆修正あり)。
近年においても、たとえば米国におけるトヨタのプリウスの不具合問題では、同社の米国法人に対して十分な裁量権が与えられておらず対応が後手にまわるなど、依然として子ばなれ、親ばなれができていない日本企業の実態が明らかとなったが、この図を見ると、トヨタ自動車でさえも、真の国際化への道のりは、まだ道半ばであるということがわかる...
(続きは下記をご覧ください)
◆企業再生請負人、経営・技術戦略コンサルタント、田中 純の「経営・技術戦略実践講座」
◆2013年12月21日、ブログ「稀代の事業家・イノベーター、所源亮さんのこと」をアップしました!

写真中央が、20万部ベストセラー経営書『ストーリーとしての競争戦略』(楠木健さん著)のなかで、ストーリーがいちばんおもしろい経営者として紹介され、世界的に希少な感染症特化型の創薬ベンチャーで成功をおさめつつあるアリジェン製薬株式会社のCEOで、一橋大学の特任教授もつとめる所源亮(ところげんすけ)さんである。
所さんは、わたしのメンター的存在で、いわば事業家としての兄貴ぶんのような方である.....
(続きは下記をぜひご覧ください!)
◆企業再生請負人、経営・技術戦略コンサルタント、田中 純の「経営・技術戦略実践講座」
◆2013年11月24日、ブログ「生物学会でもイノベーション?~東大・松井教授の《スリランカの赤い雨》出版記念対談に行ってきました!」をアップ!

本日11月25日、世界的な地球物理学者で生物学会におけるイノベーターでもある東京大学名誉教授・松井孝典さんの新刊『スリランカの赤い雨』の出版記念対談・講演会(神保町東京堂書店ホール)に、応援に行ってきた。
※写真左から、世界的な天文学者でアストロバイオロジーの権威・バッキンガム大学のチャンドラ・ウィックラマシンゲ教授、おひとりおいて、
きょうの司会で、一橋大学特任教授でベストセラー経営書『ストーリーとしての競争戦略』のなかで一番ストーリーがおもしろいといわれた伝説の創薬ベンチャー起業家でもある所源亮さん(田中のメンターでもある)、
チャンドラ博士とおそろいの赤いセーターがお似合いの松井先生、
所さんのいとこで田中との交流も深い高名な歴史版画家の原田維夫さん、
いちばん右がわたし。
(続きは下記をぜひご覧ください!)
◆企業再生請負人、経営・技術戦略コンサルタント、田中 純の「経営・技術戦略実践講座」
◆2013年10月31日~11月1日、「産総研オープンラボ2013」にCSPモデルベース開発技術の共同研究者として出展しました!

産総研オープンラボ2013、今年も盛況のうちに終了!
田中も共同研究者として「高信頼ソフトウェア開発支援/CSPモデルベース開発の普及をめざして」「複雑な並行処理可視化ツールの開発」というテーマで出展しました。そのブース前で記念撮影です。
田中は、独)産業技術総合研究所にて、構造モデリング言語に関する研究や、組込みソフトウェア開発企業への技術戦略コンサルティングから得た知見を生かし、複雑かつ巨大化したソフトウェアの解析・開発技術をその生産プロセスにどう組込み、使いこなしていくか、イノベーションにどうつなげていくか、についての研究を行っています。
写真は左から、某大手商社系シンクタンクの副社長で、われわれCSPプロジェクトチームを支援してくださっているOさん、田中、および田中率いるチームの中心メンバーで、CSP理論/並行ソフトウェア解析理論の第一人者、産総研・高信頼ソフトウェア研究グループ長の磯部祥尚博士。
(2013年10月31日撮影)
◆2013年10月27日、ブログ『戦略実務のしろうとに人気? ~ポーター事業戦略理論の問題点を考える』をアップしました。

競争戦略論の発表直後にみずからのコンサルティング会社をおこし、巨万の富を築いたハーバード大学ビジネススクールの"スーパースター"、マイケル・E・ポーター教授。
しかし、シカゴトリビューン紙記者のオシーア、マディガンの著書『ザ・コンサルティングファーム』によると、その成果には大きな疑問がのこる、といった旨の報告がなされている。
(中略)
1980年前後の発表ながら、2013年10月現在においても、解説本やこれを基盤とした論文が出され続けているように、いまでも非常に人気の高い事業戦略理論、それがマイケル・ポーターの「競争の戦略」「競争優位の戦略」である。以下、これらの理論に潜在する問題点を、とくに実務者の観点から指摘していきたい。
◆2013年10月3日、 第8回ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会を開催しました。

10月3日(木)、第8回「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」を開催しました。
今回は、オランダに本社を置き、既存のIT資産を統合・再活性化するすぐれた機能をもつ業務マネジメント・システムを世界中に展開するC社の日本法人代表、H・Kさんから数々の報告と問題提起が行われました。
↓詳細は以下でご覧ください。
◆第8回ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会を開催~業務系ITシステム業界最前線からの報告
※研究会にご興味のある方、取材等をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
◆2013年8月20日、ブログ 『実戦感覚あふれるプロ経営者、三枝匡の戦略・改革理論を読みとく』を更新しました。

~本文紹介より~
三枝匡(さえぐさ ただし)という経営者がいる。 企業再生のプロとして複数企業の再生を成し遂げたあと、FA部品・金型商社「ミスミ」の経営者へと転身し、同社を超優良企業へと生まれ変わらせた人物だ。
日本がほこる、数少ない「プロフェッショナル経営者」であり、彼のアプローチには、P.F.ドラッカー教授の理論にも通じる部分がおおいのが特徴でもある。
●企業再生請負人、事業・技術戦略コンサルタント、田中 純の
「経営・技術戦略実践講座」
『実戦感覚あふれるプロ経営者、三枝匡の戦略・改革理論を読みとく』
◆2013年8月1日、結成1周年、第7回ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会を開催!

2013年8月1日(木)、結成1周年となる第7回「ドラッカー・マネジメント&イノベーション研究会」を開催しました。
今回は、某大手電機メーカー系情報システム企業に在籍するKさんから、きびしさを増す同社の業績傾向とともに、同社が抱える根の深い病根や、今後の生き残りの可能性について、公開できるギリギリの実態報告、および問題提起がなされました。
詳しくは以下をご覧ください。
●企業再生請負人、事業・技術戦略コンサルタント、田中 純の
「経営・技術戦略実践講座」
http://blog.goo.ne.jp/jtmtanaka
◆2013年7月27日、ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所のホームページをリニューアルしました。
ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所の公式ウェブサイトをリニューアルしました。
今後も順次コンテンツを追加していく予定です。
なお、当事務所のくわしい活動内容については代表 田中純のブログをご参照いただきますようお願い申し上げます。
企業再生請負人・戦略コンサルタント、田中 純の「経営・技術戦略実践講座」
http://blog.goo.ne.jp/jtmtanaka















